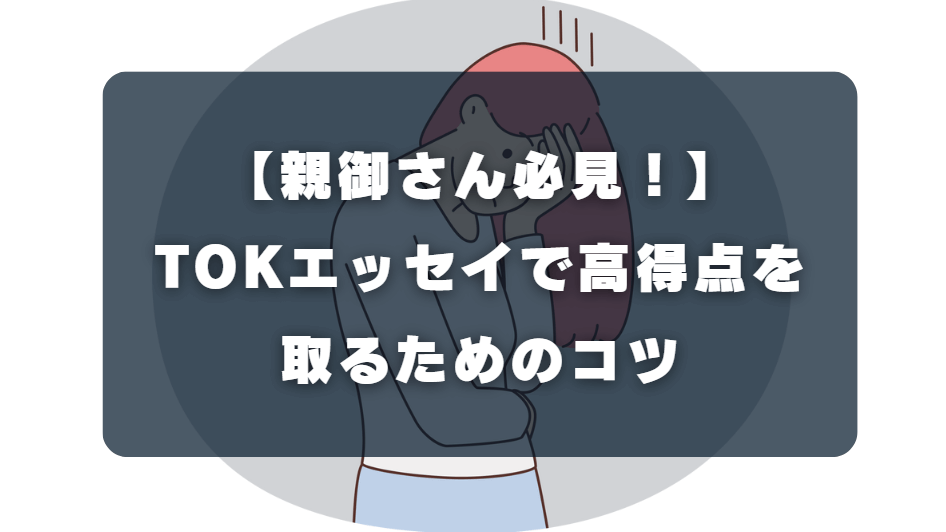IBで学ぶ“問いを深める力”とは?
IBプログラムの特徴の一つに TOK(Theory of Knowledge)=知の理論 があります。
しかし親御さんからすると「難しそう」「一体何を学んでいるの?」と感じることも多いのではないでしょうか。
TOKエッセイは、IB生が大学進学や将来に向けて大きな成長を遂げる場です。単なる「知識を説明する」試験ではなく、「問いをどう深めるか」「異なる視点をどう扱うか」を試されます。ここでは、エッセイに取り組む子どもたちが実際に意識している4つのポイントをご紹介します。
1. タイトル選びは「広がりやすさ」が鍵
エッセイでは、IBから提示された6つのタイトルの中から1つを選んで書きます。
多くの生徒は「自分の得意科目に近いもの」を選びがちですが、評価されるのは知識量そのものではなく 知識をどう比較・活用できるか です。
例えば「歴史的知識はどこまで客観的か?」というタイトルは、歴史に限らず科学や芸術とも結びつけやすく、自然に多角的な議論が広がります。
親御さんから見ると、子どもが悩んでいるときに「広い視点で書けそうなテーマを選んでみたら?」と声をかけるだけで支えになるでしょう。
2. 例は「正しさの証明」ではなく「議論を広げる」ために
エッセイには実例が欠かせません。
ただし多くの生徒が「主張を裏付けるため」だけに例を使いがちです。
本当に評価されるエッセイは、例を使って議論をさらに広げています。
たとえば「科学は客観的である」という主張にDNA鑑定を挙げた後、
「しかし研究資金の出どころや社会的背景によって解釈は変わらないか?」と問い直す。
こうすることで「単なる証明」ではなく「より深い思考」につながります。
お子さんが例を探しているときには、「その例って、違う角度から見るとどうなるかな?」と問いかけるのも良いサポートです。
3. 定義はゴールではなくスタート地点
エッセイでは「客観性」「知識」などのキーワードを定義します。
しかし、定義して終わりではなく、そこから議論を展開するのがポイントです。
たとえば「客観性=観察者に依存しない性質」と定義した後に、
「しかし歴史では誰が記録したかによって“客観的事実”は変わってしまう」と続けると、定義が生きた議論に変わります。
親御さんは「難しい言葉の定義を書いている」子どもを見ても、それが単なる暗記や説明ではなく、自分の思考を深める出発点になっていることを理解してあげると良いでしょう。
4. 結論は「答え」ではなく“問いを再提示する場”
エッセイの最後に「結局〇〇だ」と答えを書きたくなりますが、それはTOKらしくありません。
高評価のエッセイでは、結論は「問いをもう一度考え直す場」として使われます。
たとえば「知識は常に変化する」と議論した場合、
「むしろ本質的な問いは、なぜ私たちは変化を受け入れるのかではないか」と広げて締めくくります。
親御さんからすると少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、これは子どもが 「答えの出ない問い」と向き合う力 を育てている証拠でもあります。
まとめ
TOKエッセイは「正しい答え」を出すためのものではなく、問いを深め、複数の視点から考えるためのものです。
- タイトルは「広がりやすさ」で選ぶ
- 例は「議論を動かす」ために使う
- 定義は「出発点」として扱う
- 結論は「問いを再提示する場」とする
このプロセスを通じて、子どもたちはただ知識を覚えるのではなく、「考える力」を磨いています。
TOKに取り組む姿を見守ることは、親にとっても「我が子がどのように世界を理解しようとしているか」を知る機会になるかもしれません。